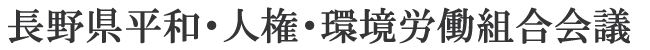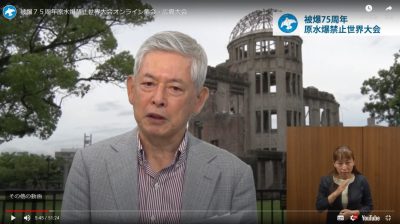憲法記念日の5月3日、県内各地で憲法を護り活かす立場からさまざまな集会が開かれました。長野市では、ジャーナリストの竹信三恵子さんより、コロナ禍で浮き彫りとなった「女性不況」といわれる雇用問題から生存権など憲法理念の自洗と実現が必要であることを学びました。松本市で行われた集会では、平和憲法が持つ世界的な先進性について再確認されました。
◆コロナが直撃した女性の雇用問題
長野市で開かれた第30回市民の憲法講座(信州護憲ネット主催)では、長年女性の貧困問題を取材してきたジャーナリストで和光大学名誉教授の竹信三恵子さんがオンラインで講演。コロナ禍で浮き彫りとなった「女性不況」の実態を通じて憲法が保障する生存権や9条の意義について考え合いました。
竹信さんは、働く女性の過半数が非正規雇用であること、さらにコロナ禍で深刻な打撃を受けた対人サービス業の雇用者のおよそ60%が女性であるという構造的な理由からコロナ不況は女性を直撃し、「脆弱な女性の雇用が浮き彫りになった」と指摘しました。
また、非正規も対象となるはずの休業補償が、雇用主の誤解や煩雑な手続きへの敬遠から本人に補償が届かない事例があること、さらに、健康保険ではコロナ発症により給付される「傷病手当」が、非正規が多く加入する国民保険では当初対象外であったことなどを述べ、「非正規への公的ネットワークの不備」を問題視。コロナ禍で行った女性向けの相談会であった、「生活が苦しい」「住むところがない」といった相談内容を示し、憲法25条で保障される生存権がおびやかされていると指摘しました。一方、コロナ禍による労働問題に対し取り組んだ労働組合や市民団体の活動については、困窮者の支援につながった事例を紹介し、こうした活動を憲法理念の実践として評価しました。
社会保障の整備に必要な国の財政についても憲法と照らし合わせて解説された。1894年の日清戦争にはじまり、1945年までの戦争をする国であった日本の財政構造について、69%から最大で85%が軍事費に使われてきたと示し、「戦争時には財政が人に使われない」「9条をいいかげんにしたら財政が人の幸福に使われるのか、一般の生活に公的資金が回るのかを疑問に思わなければならない」と、安易な9条改憲議論に流されないように警鐘を鳴らしました。
最後に、「護憲とは9条を守るだけではなく、生存権・幸福追求権など憲法全体の構造を活かしていくこと」と強調し、「活憲」への不断の努力を呼びかけました。
◆ 世界の歴史を先導する9条
松本市の会場では、中信市民連合が主催し、花時計公園で「新型コロナと憲法~自由と制限を考える」集会が開かれました。ゲストトークでは、名古屋大学名誉教授の池内了さんから「世界の歴史を先導する憲法第9条!」と題する講演を受けました。
池内さんは、「人類の歴史は、戦争・暴力・軍事力に頼る『野蛮』と、平和・軍縮・話し合いによって物事を決める『文明』が絶えず拮抗してきました。その中で世界が戦争放棄を求め、武力に頼らないという流れを先導したのが、日本国憲法の第9条である」と述べました。
また、現在のミャンマー情勢から、軍隊を持つことの危険性に触れ、軍隊は国民を守るのではなく国を守るものであり、今回のクーデターのように「国を守る目的」で、自国の国民を弾圧し、見捨てることもあると指摘しました。その上で、日本同様、世界で唯一軍隊を持たないことを憲法に記すコスタリカと日本とを比較し、「コスタリカの大統領は永世的、積極的、非武装中立を宣言している一方で、日本のトップは自国の憲法をみっともないといい、軍拡路線へつき進もうとしている」と批判しました。
最後に、今年1月ついに発効された核兵器禁止条約に日本が批准していないことについて、「条約に批准し、核廃絶を訴えていくことは、世界史を先導してきた憲法9条をもつ日本の役割である」と強く訴えました。